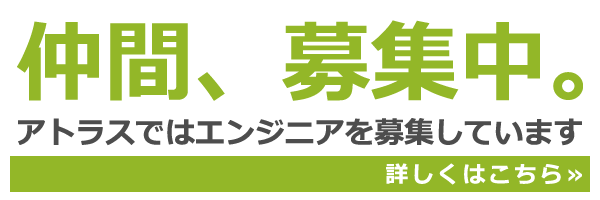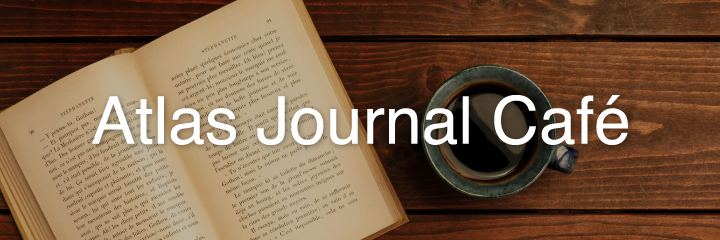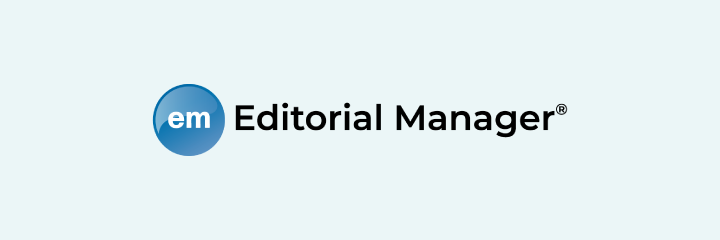生成AIを活用し、2週間でKotlinをキャッチアップ
目次
こんにちは、システムエンジニアのキュウです。今年のSMOOSYの新機能開発を通じて、私はメイン開発言語をKotlinへ切り替えることに挑戦しました。
アトラスでは、2023年からコーディング支援ツールのAIを導入しました。今回は生成AIを活用して、JavaからKotlinへの移行を効率的に進め、短期間で核心的な知識を習得し、プロジェクト開発に参加できるようになったプロセスを共有します。同様の技術移行に取り組む方や、AI支援学習に興味をお持ちの方の参考になれば幸いです。
ステップ1:Javaとの差異に焦点を当てた学習計画を作成する
経験のある開発者なら、新しい言語を学ぶ最も効率的な方法は既存の知識と比較することです。「変数」のような基本概念から学び直すのではなく、プログラム言語のどこが同じでどこが違うのかに注目するのが鍵となります。
そこで私はAIに明確な指示を出し、自分に最適化された学習計画を生成してもらうことにしました。
質問例:
|
1 2 |
私はJavaを使ったプロジェクト開発の経験があります。これからはKotlinを学び、次のプロジェクトで活用する必要があります。 短期間で習得でき、かつ私に適したKotlinの学習計画を立ててもらえますか? |
AIの返答(一部抜粋):
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
Java経験者のためのKotlin速習2週間プラン このプランの目標は、「2週間でKotlinの主要な機能を理解し、プロジェクトで読み書きできる状態になること」です。 Javaとの違いを意識しながら進めるのが最短ルートです。 1週目: Kotlinの基本と「お作法」をマスターする まずはJavaとの構文の違いに慣れ、Kotlinならではの安全で簡潔な書き方を学びます。 中略 1週目のゴール: • Javaの冗長な記述(getter/setter, equals, hashCodeなど)が、Kotlinでいかに簡潔になるかを実感する。 • NullPointerExceptionを恐れないプログラミングスタイルに慣れる。 • IntelliJ IDEAの「JavaコードをKotlinに変換」機能を活用して、学習を加速させる。 中略 2週目: Kotlinの真価を発揮する関数型プログラミングと実践 Kotlinの表現力を飛躍的に高める、より高度な機能に取り組みます。 中略 2週目のゴール: • ラムダ式やコレクション操作を使いこなし、簡潔で流れるようなコードが書けるようになる。 • 非同期処理の基本的な書き方を理解し、プロジェクトで出てきても戸惑わない状態になる。 • 既存のJava資産を活かしながら、Kotlinで開発を進めるイメージが掴める。 後略 |
この計画は、学習プロセスでの目標を地図のように明確に示してくれました。おかげで膨大な情報の中で迷うことなく、効率的に学習を進めることができました。
ステップ2:慣らしコードで、新しい知識を実践する
Kotlinの基本文法を理解した後は、実践を通じて知識を定着させる必要があります。
いきなり実際の業務コードに取り組むのはハードルが高いと感じるかもしれません。
そこで私は、以前Javaで作成したソースコードをAIにKotlinへ書き換えてもらい、詳細なコメントを付けてもらいました。
質問例:
|
1 2 3 |
私はJavaで重複ファイルを検索するプログラムを作成しました。 同じ機能をKotlinで実装し、詳しいコメントを付けてもらえますか? [Javaのソースを添付] |
AIの返答(一部抜粋):
|
1 2 3 4 5 6 |
ご作成されたJavaの重複ファイル検索プログラムを、より現代的で簡潔なKotlinのコードに変換し、Java経験者の方が理解しやすいように詳細なコメントを付け加えます。 Kotlinでは、Javaの冗長な記述を大幅に削減できるデータクラス、拡張関数、スコープ関数などの機能が非常に役立ちます。 DuplicateFileFinder.kt (Kotlin版) 以下がKotlinで書き直したプログラムです。Javaのコードと見比べながら、Kotlinの簡潔さや安全性を実感してみてください。 後略 |
もともとのロジックは自分で書いたものだったため、AIが生成したKotlinコードと比較することで、各ステートメントの意図と実装方法を容易に理解できました。
このプロセスは「Javaの思考法」から「Kotlinの思考法」へと効率的に移行し、新しいプログラミングスタイルに適応する上で非常に役立ちました。
ステップ3:AIを、いつでも質問できる技術パートナーにする
学習の過程では、理解が難しい概念に必ず出会います。私の場合、Kotlinの「拡張関数」という概念に最初は戸惑いました。
以前なら、多数のブログやドキュメントを調査したり、開発者コミュニティで質問を投稿し回答を待ったりする必要がありました。
今では、AIを自分のペアプログラミングパートナーとして活用し、直接質問できるようになりました。
質問例:
|
1 2 |
Kotlinの拡張関数ですが、具体的な例について詳しく説明してください。 また、拡張関数はJavaのユーティリティクラスと同じような利用シーンと考えてよいのでしょうか。 |
AIの返答(一部抜粋):
|
1 2 3 |
Kotlinの強力な機能の一つである「拡張関数」について、その概念、具体例、そしてJavaのユーティリティクラスとの比較を交えて詳しく解説します。 拡張関数の概念 拡張関数とは、一言で言うと「既存のクラスを継承することなく、そのクラスに新しい関数を追加できる機能」です。まるでそのクラスにもともと備わっていたメソッドかのように、新しい関数を呼び出すことができます。 後略 |
さらに質問したら:
|
1 |
拡張関数を大量に使用すると、大規模なプロジェクトでは混乱を招く可能性はありますか? たとえば、かつてのC++プロジェクトで演算子オーバーロードが乱用されたようなケースのように。 |
AIの返答(一部抜粋):
|
1 2 3 4 5 6 |
はい、その懸念は非常に的確です。拡張関数を無秩序に大量使用すると、大規模プロジェクトではC++の演算子オーバーロードの乱用のように、コードの混乱を招く重大なリスクがあります。 機能自体が問題なのではなく、その使い方に規律が求められるという点で、両者は非常によく似ています。 混乱を招く具体的なケース 拡張関数が問題を引き起こす典型的なパターンは以下の通りです。 1. 名前空間の汚染と可読性の低下 後略 |
AIは説明に加えて、具体的なコード例やベストプラクティスの提案も提供してくれます。
このような即時フィードバックを得られる学習方法により、疑問解決の時間が大幅に短縮され、コードのロジック自体に集中できるようになりました。
最後に:AIは開発者の学習加速器(アクセラレーター)です
開発者として、生成AIが以下の点で非常に役立つことを実感しました:
- 情報収集の効率化:膨大な情報の中から核心部分を迅速に整理・提示してくれるため、情報検索の時間を大幅に短縮できます。
- 気兼ねない質問相手:優秀なメンターのように、初歩的な質問から複雑な問いまでいつでも答えてくれます。「こんな質問をしても良いだろうか」と躊躇する必要がありません。
- 新たな発想の源:その幅広い知識を通じて、対話から新しいアイデアやインスピレーションを得られることもあります。
生成AIを積極的に活用し、自身のスキルアップにつなげていきたいと考えています。